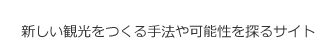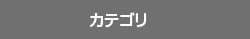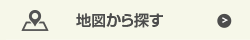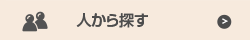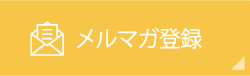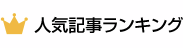境界協会の主宰・小林政能さんに聞く! 境界線の魅力とまちづくりへの可能性

埼玉県・栃木県・群馬県の3県境で撮影した集合写真。2017年3月19日に行われたフィールドワークでは、36名が参加した。最後のページに参加レポートを掲載する
なぜ境界線?
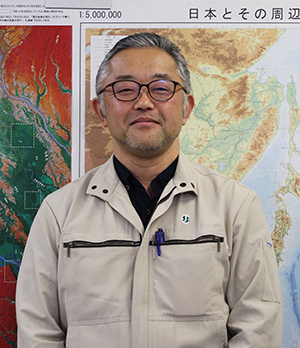
境界協会主宰を務める小林政能さん
小林さんは、一般社団法人日本地図センターで雑誌『地図中心』の編集に携わっており、その他にも地図センター主催の「夏休み地図教室」や各地の講演会で講師を務めるなど、地図や地理空間情報の普及活動も行っている。もともと地図が好きだったという小林さんは、境界線が公園や競技場の敷地内に引かれていることが前々から気になっていたという。
そんな彼が、境界線に着目したフィールドワークを企画するようになったきっかけは、自身が編集している『地図中心』の企画にあった。
小林:『地図中心』2014年3月号で、「葛飾区境をみんなであるいてみた!」という企画を実施しました。この取材に私も同行しまして、境界線をめぐることの面白さを実感したのです。
その後すぐに境界協会を立ち上げ、2014年5月には初めてのフィールドワーク「文京区VS台東区+α」を開催した。以降、フィールドワークは約2カ月おきに行われ、現在までに全19回が開催された。今年1月に行われた、杉並区・三鷹市・世田谷区・調布市の境界線をめぐるフィールドワークでは、80人以上の一般人が参加した。参加者には女性も多く、年齢層は20~80代と幅広い。
小林:フィールドワークでは、時速2kmのゆったりとした速度で歩くため色んな人が参加しやすく、老若男女、参加者を問わないイベントと言えるかもしれません。地元からの参加もあり、住んでいる人しか知らない情報を教えてもらうこともあります。そういうお話をお聞きするのも、フィールドワークの面白さ一つです。
スポンサードリンク