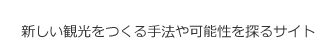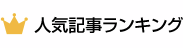水と光の観光まちづくり 「水都大阪」の再生から成長に向けて

堂島川沿いにあって、水上レストランやカフェで賑わう中之島バンクス
世界の水都再生と大阪
文明は川の流れとともにあり、都市は水際に発達する。世界各地に「水の都」の名にふさわしい都市がある。欧州では、例えばアドリア海に面した都市国家ヴェネチア、河港として栄えたストラスブールやブルージュ、河口に築かれたアムステルダムなど、河川を利用した水運が繁栄の礎となった歴史都市は多い。
アジアの諸都市も同様である。タイでは、アユタヤ、トンブリーなど、各王朝が国土を貫流する川に沿って都を築いた。今日の首都であるバンコクも、チャオプラヤーの流れとともに繁栄をみた。中国では、太湖や西湖などの湖岸に発展した無錫(むしゃく)、蘇州、杭州などを連絡するべく、京杭大運河が開削された。内陸の水運が、国土の動脈となったわけだ。
一方、川に面したブラウンフィールドの再開発が、都市を活性化する契機となり、成功した事例も多い。米国では、リバーウオークの再生によって、南部有数の観光都市に転じたサンアントニオなどは、最も早く成功した事例である。近年では、パリ、ロンドン、ビルバオ、バーミンガム、ソウルなどを列挙することができる。
大阪も「水の都」と呼ばれて久しい。都市再生を進める枠組みのなかで、私たちが「水都大阪の再生を」と声をあげたのは、2001年に遡る。大阪の水辺の再生事業も、この春からは官民連携の新たな組織「水都大阪コンソーシアム」を設けて、次のフェーズに向けて動き出した。その経緯について、簡単に紹介しておきたい。
「天下の台所」から「水の都」へ
私は、大阪の都心に生まれ、東横堀川や道頓堀を眺めながら育った。汚れきった泥まみれの川と、高架道路に光を遮られた暗い川岸が原風景である。やがて故郷の都市再生に関わることになり、私がこだわったのは、河川及び水路を軸とした地域の再生、いわゆる「水都再生」である。その背景には、記憶のなかに染みついた異臭の漂う暗い川筋を「光のあたる場に、健やかで多くの人が集う場に改めたい」という強い想いにある。
よりどころは、大阪の歴史にある。古くは「難波津(なにわつ)」の時代から、大阪は海外から人や文化が往来する国際交流拠点として発展した。また近世には、各藩の蔵屋敷が置かれ、米市場で取引がなされ、諸国の物産が集積する経済の中心地となった。「天下の台所」という異名をとるほどに存在感を示した商都大阪における諸活動を、縦横に開削された運河や掘割のネットワークが支えた。
淀川を通じて京と結ぶ舟運、大阪湾を経由して全国各地を結ぶ廻船、金比羅参詣の船などが、この街を拠点とした。同時に伊勢や高野・熊野などを結ぶ街道の起点でもある。大阪は水陸交通の要にあって、先例のない都市を築いた。
近代になっても状況は変わらない。公共施設やオフィスが集積しビジネスセンターとなった出入橋や中之島、道頓堀の興行街、東横堀川に沿った倉庫街、証券業が集積した北浜、材木商が集積した長堀など、個性的な界隈が川筋に面して連鎖した。
大川や寝屋川沿いには、造幣局、砲兵工廠などの官営工場群、木津川や安治川沿いには紡績や機械関連の製造所、造船所などが立地した。林立する煙突群は、「東洋のマンチェスター」と呼ばれるようになる。
一方川筋には、都市を先導する美観がつくられていく。明治時代後半、水路に面して洋館やビルディングが集積する景観は、パリやベニスと比べられ、「水の都」あるいは「水都」という美称で呼ばれるようになった。その後、大正や昭和初期、道路拡幅に応じて中之島・西横堀川・東横堀川などにかかる橋梁を刷新した際には、パリを意識して質の高い美しいデザインが採用された。
しかし戦後復興から高度成長を果たすなかで、その役割を終え、多くの河川は埋め立てられ、水路の上、あるいは堀川の跡を高速道路が縫うように建設された。背景には、水運の減少、川沿いへの工場立地、水質悪化などがあった。また高潮や洪水対策の必要性から堤防が構築され、市街地と河川空間は遮断された。私たちの日常生活のなかで、河川の存在を意識する場面は減じた。
結果、水路に背を向けつつ、都市が発展することになる。戦後の繁栄は、かつての「水都」の魅力を忘却することで得たものであると言って良い。

昭和初期の中之島公園 遠くには工場の煙突が点在している
スポンサードリンク