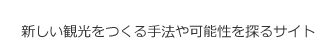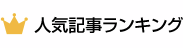水と光の観光まちづくり 「水都大阪」の再生から成長に向けて

ラバーダッグは2007年に制作されたアート作品。ヨーロッパ、南米、アジア、オセアニア、中東、北米など世界中で展示が行われている。公共の河川や海などの水辺をバスタブに見立て、街並みを背景に取り込んだアート。大阪では2009年以降、「水都大阪」のシンボルとなっている。
「水の都大阪再生構想」と「水都大阪2009」へ
状況が変わったのは90年代半ばのことだ。1995年(平成7年)、大阪リバーフロント整備推進協議会が「大阪リバーフロント整備のグランドデザイン」を、さらに大阪市計画局が「新・水の都大阪グランドデザイン」をとりまとめ、方向性が示された。
もっとも具体化をみるのは21世紀になってからのことだ。2001年(平成13年)12月、政府は「水の都大阪再生事業」を都市再生プロジェクトに決定した。これを受けて新たな枠組みとして2002年(平成14年)10月、大阪商工会議所会頭の田代和氏を会長に、大阪府、大阪市、経済界が一体となり「水の都大阪再生協議会」を設置、私もアドバイザーとして参画しつつ「水の都大阪再生構想」がまとめられた。
「美しい水辺のまちをつくる」「心に響く水辺の賑わいをつくる」「水辺をネットワークし魅力を高める」「やすらぎの水環境をつくる」という4つの基本方針を掲げ、構想では「輝け 水の都大阪 ~時を感じる水の回廊」とうたった。市民、NPO、経済界、行政、学識者などが協力、「水の都」を再生することから、「21世紀のモデル都市」かつ「国際集客都市」の実現を図ろうとする志が示された。
注目されたのが「水の回廊」という言葉に託された都心の河川ネットワークである。大阪では、大川、土佐堀川、堂島川、木津川、東横堀川、道頓堀川が、船場、島之内、堀江と呼ばれる都心を矩形に囲んでいる。多くの運河が埋め立てられたなかで、かつての水都の面影を伝える河川群である。
構想では、ゾーンごとにハードを整備して、川筋ごとに魅力を高めることが企図された。道頓堀川ではウッドデッキによる遊歩道を整備、一方中之島や大川沿いでは京阪電鉄の新線建設に応じて、公園や親水空間の再整備が具体化してゆく。
ハードだけではない。水都再生に向けた市民の機運を高め、「水都を支える集客システムの構築」「水都大阪の魅力あるイベントの開発(花と緑、光と水を活用したイベントの展開)」を柱として、新たな観光集客につなげるべく、ソフト事業を重く見る考え方もここに示された。
中之島の再整備が進展した2009年をシンボルイヤーと位置付け、「水都大阪2009」と命名したシンボルイベントを実施した。私と北川フラムさんがプロデューサーを務め、アートイベントを展開した。千島土地株式会社の協賛を経て、オランダ人作家による作品を浮かべるラバーダック・プロジェクトが人気を集めた。
イベントを契機に、さまざまな船が運行するようになる。イベント時には、口から火を吐くヤノベケンジ氏の作品「ラッキードラゴン号」も運行した。
堤防や橋梁の照明をLEDに改める事業にも着手、また公園のライティングも河川や船からの眺めを意識したものに改めた。中之島の東端には川の水を汲み上げて、浄化して打ち上げる噴水も整えられた。先行して実施していた中之島での催事「光のルネッサンス」に、恒常的な夜景が加わったことになる。その後も継続して、川沿いに限らず都心における夜景創出の事業は、私が委員長をつとめる「光りのまちづくり委員会」が、官民連携のもとにまとめた構想に沿いつつ推進されている。

白色またはオレンジ色の光で交互にライトアップされる中之島公園大噴水と八軒屋浜
忘れられた水辺を交流空間として回復
私が企図したのは、交流や観光集客の場としてリノベーションすることで、舟運が衰え、忘れられた河川空間の回復を図りたいという点だ。先例は各国にある。90年代、シンガポールでは、川筋にある古い倉庫地区を魅力的な飲食店街に転換して成功をみた。ソウルでは高架道路を撤去、人々が時間を過ごすことができるせせらぎに転じさせた。
産業革命の先駆けである英国にも学ぶべき先行事例がある。マンチェスターと郊外の炭鉱を結んで開削されたブリッジウオーター運河を手始めに、内陸の産業都市群と港湾を連絡する水運のネットワークが構築された。しかし鉄道や道路の発達で、舟運は主役の座から追われる。そこで1968年に制定された交通法では、レジャー船や釣り人の利用を前提とする水路、健康やアメニティのために必要な水路といった分類が示された。役割を終えた交通基盤に、新たな機能を託したわけだ。
河川沿いの再開発の気運が高まるのは80年代、サッチャー政権下のことだ。都市開発公社やエンタープライズゾーン制度の導入を契機に、各都市では内陸水路沿いにある遊休地の再整備が進んだ。またバーミンガムやロンドンのように、河川を軸とした都市再生も進展する。
そもそも英国の人々は、河川に関する「通行権」に対する想いが強い。主要な運河を管理する公益法人ブリティッシュ・ウオーターウェイズは「Access for All(すべての人にアクセスを)」をスローガンに、水路沿いの側道を一般に開放、また随所に船の短期係留場所を確保している。河川空間は市民が使いこなす場所、とみなす発想がある。
日本の都市とは対象的だ。わが国では、河川の利用は自由であり、法的な制限はない。しかし川岸の管理は厳密である。水際まで降りることができる親水護岸も以前よりは増えたが、ほとんどの岸辺は船の着岸を想定していない。近年になって「防災」をうたい文句に公共桟橋の整備も進んではいるが、緊急用であるがゆえに通常の利用は少ない。
公共空間に対する意識が異なるため、英国にあるような水際を整えることは現状では難しいだろう。しかし大阪に限らず、水際をもっと活用し、人々のさまざまなアクティビティを受け入れる場にすることができないだろうか。
大阪の水都再生においては、水際の交流の場づくりにこだわった。私は「水辺の名所」を現代的に再創造することが必要だと説いてきた。
一例が天満橋駅に接する八軒家浜である。珍しい地名は、この場所に八軒の旅籠(はたご)があったことに由来する。かつては大坂と京都の伏見を結ぶ三十石船の発着場であり、かつ熊野街道の起点となった。淀川舟運と陸路と連絡する結節点であった場所だ。
その再整備にあたって、私は「浜」という接尾語にこだわった。かつて大阪には、市街地の至るところに「◯◯の浜」と呼ばれる親水空間があった。大阪が水都再生をうたうのであれば、誰もが水辺に近づくことができ、さまざまな船が停泊することができた大阪独自の「自由空間」、すなわちかつての「浜」を復活させることが第一だと思ったからだ。
その後、八軒家浜には、大阪商工会議所都市再生委員会の尽力もあって、「川の駅」が設けられることになる。伝統を継承する「浜」の一文字に、水都再生への私の想いが込められている。
中之島界隈では、河川空間での賑わいづくりがさらに進展した。2009年、河川法の準則緩和を受けて、民間による利活用が進展した。中之島バンクスやラブセントラル、北浜テラスなど、民間事業者が河川空間の利活用を実施する事業が具体化した。また歩行者専用の橋梁の上に仮設店舗を設けて、イベントを展開する社会実験も行った。
私は、現代的な「川床」の再生を図りたいと考えた。近世初頭の大坂を描いた屏風絵を眺めると、水路にせり出すように床を設けている店が描かれている。また江戸時代から大正時代に至るまで、八軒家から北浜、難波橋周辺の土佐堀川沿いでは、川筋に料理旅館が軒を並べていた。古い絵図や、明治から昭和初期の写真を見ると、川側に縁をせり出し、眺望を売り物にしていた店もある。また屋根の上に物見台のような縁台を設けて、そこで宴をしている例もある。
天神祭の花火見物には特等席となったことだろう。床席とは異なるが、川面をわたる涼風を浴びて一時を楽しむ納涼の場になっていた。
さまざまな目的で川縁に人々が集い、出会い、交歓し、情報を交換する。かつての水辺での楽しみ方を想起させる現代的な「川床」は、水際をコミュニケーションの場として再生する試みである。

土佐堀川に面する「北浜テラス」。中央公会堂や川を間近に感じながら食事を楽しむことができる
スポンサードリンク