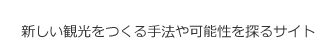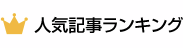連載「地域ブランドの作り方」成功のための12のハードル ~その2.ブランディング、なぜ必要?「目的の共有とブランド定義づくり」のハードル~
ブランド定義づくりの重要性
多くのブランド化を目指す取り組みでは、この定義づくりの合意形成に苦労しているケースが見受けられます。信頼されるブランドになるために必須の、優位性を持ったブランド定義づくりがハードルになっているようです。2018年5月22日の日本経済新聞に、次のような記事が掲載されていました。「ご当地産品、絶えぬ本家争い」というタイトルで。国の地理的表示(GI)制度で認定されている「八丁味噌」について、江戸時代から八丁味噌を製造する2社(同組合には加盟していない)が「にせもの」として排除されていることを不服として、所管省庁である農水省に行政不服審査を申し立てた、というものです。ここで重要なのは、GI登録の主体となった組合では製造時に金属製のタンク利用を認めているのですが、この2社では「木おけで熟成させる昔ながらの製法こそが八丁味噌」だと、商品定義の部分で意義を申し立てていることです。どうでしょう、ここでは八丁味噌の何を価値として信頼を得るのか、何が優位性なのか、関係者の合意形成ができていない段階で申請をしたのでしょうか、詳しいことは分かりませんが、問題は「何を大切にして、信頼を得る八丁味噌として販売するのか」というブランド定義の合意形成の問題に行きつきます。
うまくいっている事例を見てみましょう。それは、JA鶴岡が取り組み、成功した「だだちゃ豆」です。JA鶴岡では、昭和61年にJA鶴岡茶毛枝豆専門部(現在は「JA鶴岡だだちゃ豆専門部」)を設置し、京浜方面に枝豆の出荷を始めました。この枝豆は、江戸時代から殿様に献上されるなど、地元では評判がよく高値で取引されていましたが、実際には輸送上での品質劣化などにより京浜方面での市場評価が得られず、320キログラム程度の出荷実績にしかならなかったようです。そこで、平成2年から包装資材を変え、品質の保持、予冷の徹底を図ることによる鮮度保持、形質統一のための採種の一元化、栽培エリアの特定などの定義づくりに取り組み、加えて平成9年に「だだちゃ」という商標の独占使用権を取得、JA鶴岡と鶴岡市だだちゃ豆生産者組織連絡協議会が生産販売管理を行うことによって大きな成果を上げました。実績値としては、平成元年には生産圃場面積が510アールで700万円の売り上げでしたが、それが平成24年には300ヘクタールの生産圃場へと拡大し、約938トン売り上げ10億円近くまで伸びています。

ブランドを維持するために厳しい縛りが設けられているだだちゃ豆 写真提供:やまがた観光情報センター
ポイントは、ブランドを維持するために非常に厳しい縛り(定義)を設けたことです。まず第1は種子、6系統を選定しています。確実に種子の由来がはっきりするものを使い、専門部会が定めた種子以外は使わないということです。同時に、栽培の方法では、マニュアルを作ってそれに沿った栽培を義務付けています。基本的にはこういう栽培でやってください、土壌については必ず土壌分析をし、足りない部分については肥料なり堆肥を補うという土作りもきちっとやる、ということになっています。栽培エリアについても範囲を決め、白山地区が栽培のメインとなりますが、小真木(こまぎ)地区などでも栽培されています。そして出荷の検査も非常に厳しく、いわゆる2粒ザヤがだだちゃ豆の基本ですが、2粒ザヤ、3粒ザヤをA品とし、1粒ザヤはすべて格外品としています。加えて、予冷庫に入れずに持ってこられたものは、味が落ちるので除外になるそうです。
このように、定義を厳しく設けることによって「だだちゃ豆」は成果を上げてきました。この定義の中で、特に重要だったのは「種子」の特定です。江戸時代から続くだだちゃ豆の栽培は、地元では白山地区が本家だと認識はされていましたが、小真木地区でも「小真木だだちゃ」を栽培する農家もあるなど、複数の元祖、本家が存在していました。この状況において、丁寧に話し合って種子を6系統に絞り「だだちゃ豆」として流通する商品として管理したことが大きな成果につながったポイントになっています。 (詳しくは、正林商標特許事務所資料を参照)
スポンサードリンク