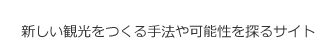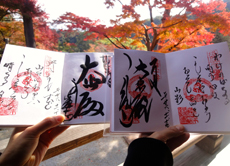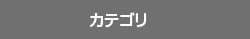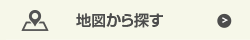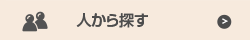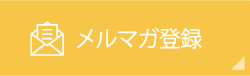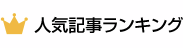よりよき観光文化の継承にむけて 第4回 “づくり”こそがよりよき観光文化継承の鍵
よりよい観光文化は、よりよい生活文化から

大油揚げづくり(狐の夜祭り)
先日、高柳町(新潟県柏崎市)の狐の夜祭りに行ってきました。
町の活性化を図るふるさと開発協議会ができたのが昭和63年、その第4分科会が母体となってできたグループ「ゆめおいびと」が狐の夜祭りを始めたのが平成元年、26回目の祭りが終わりました。当時3万人程度だった観光客が、温泉や宿泊などの施設「じょんのび村」の整備などさまざまな地域の人々の動きにより40万人と増え、そして減少し、今は適度なところで落ち着いているのではないでしょうか。
そして今、合併10年目を迎え、組織改編という新たな対応を迫られています。一方では、食を生かした観光の推進、茅葺き集落の保存と活用、宿泊型農業観光の推進など、地域は休むことなく脈々と動いています。大地の学校という新たなプロジェクトも立ち上がっています。
こうした少しずつ動いている地域を見ていると、よそ者でも一緒に考えながら何かついていけそうな気がします。なぜなら、地域の文化、高柳の生活文化が常に見えているからかもしれません。初めて訪れた高柳で、次の日の朝いろりで焼いたおにぎりの美味しさが、今でも生きているのです。
ニューツーリズムといわれるカタカナツーリズム、B級グルメ、クールジャパン等々、新たな視点のように思われる方向性が、ややもすると地域の日常の文化をおざなりにしてしまいかねません。
先日、ペットツーリズムをテーマにしたシンポジウムの案内がきました。盲導犬への対応のほうが先のように思うのですが。盲導犬は犬ではなく人の一部です。よってペットとは別なわけですが、我が国ではその盲導犬の対応すらできていません。
儲かるところに触手を伸ばすのは分かりますが、本来交流において学ぶべき文化、創造する必要のある文化への意識を持つことが、よりよき観光文化の形成において不可欠ではないかと思います。
簡単なまとめ
地方自治法第一編総則の第一条の二では“~地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、~”と書かれています。この文面は観光振興を推進するとき、重くのしかかります。昭和50年前後、この文面から、行政から観光がなくなったことがあります。観光客は住民ではないからです。
行政における観光振興は、観光客に目的達成の満足を提供することにより、最終的には住民の福祉の増進につながっていく観光振興を推進しなくてはなりません。
そうすることにより、住民の生活から成り立つ文化と、観光客との交流の中から生まれて住民に受け入れられる文化が相乗し、よりよき観光文化の形成と生活の中に息づく観光文化の継承が図られていくのではないかと思います。(終)
よりよき観光文化の継承にむけて 第1回 ニューツーリズムと従来型観光
よりよき観光文化の継承にむけて 第2回 地域資源と観光資源
よりよき観光文化の継承にむけて 第3回 観光文化の立ち戻り
■著者プロフィール

1972年社団法人日本観光協会に入協。計画調査課長、調査部長、総合研究所長を経て、2008年より現職。NPO法人観光文化研究所理事長、内閣府・国土交通省観光カリスマ選定委員会委員なども務める。専門分野は観光計画・調査、観光行政、造園計画。
スポンサードリンク